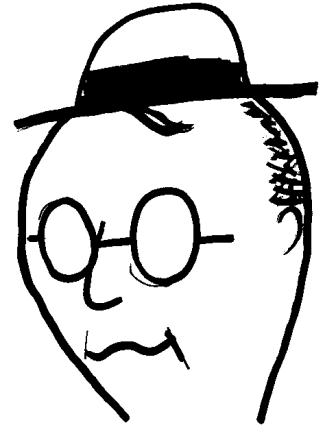オーナーあいさつ
植野農園は父が始め,私の妻が引き継ぎ,妻亡き後,私が細々と続けています.
野菜・果実・キノコなどの栽培のほか,養蜂・養鶏をしてます.
最初は,シカ・イノシシ・サル・カラス・イタチ・キツネ・ハクビシンなどの獣害にあっていましたが,周りには鉄柵,サル対策用の電柵を設置し,私が開発した忌避剤をつるすことで,現在では,獣害被害は無くなっています.時折,ネズミが出没しているようですが,獣害とは言えないレベルです.ところが最近,周辺の金属ネットなどが劣化し,穴を開けられ,ニワトリが襲われました.油断禁物です.
2020年から太陽光発電(約4kW)と蓄電池で農園の電力需要を補っています.
Farm 記録
UENO Farm Sky View
第1期太陽光発電設備(約38kW)2019年稼働

ニワトリの飼育
烏骨鶏(黒い烏骨鶏と白い烏骨鶏)一般的に烏骨鶏は白が7割,黒が3割といわれています.有精卵と無精卵を生んでくれてます.
比内鶏・比内地鶏(秋田の比内鶏雄とお隣のロード種の雌を掛け合わせた比内地鶏がいます)有精卵を生んでくれてます.
雄鳥は,果樹園に放し飼いにして,雑草処理を担ってくれてます.時間をわきまえずに鳴くのでうるさいです.
烏骨鶏の卵と比内(地)鶏の有精卵は,ちかくの「ぬくいの郷」で販売してます.
ミツバチの飼育
日本ミツバチ
西洋ミツバチ
どうも近隣の農家さんがネオニコチノイド系の農薬を散布しているらしく,この数年,ミツバチは激減.2021年には,ミツバチを数匹しか見かけませんでした.最近はクマバチであろうか,違うハチが花粉に群がっている.養蜂はもう無理か?!
詳細は「体験メニューの養蜂の欄へ」
主な栽培作物品種紹介 2022収穫物
| カンキツ系 | ネーブル | ||
| スダチ | |||
| 甘夏 | |||
| 日向 | |||
| レモン | 甘いレモンもあります | ||
| 柚子 | |||
| デコポン | |||
| キンカン | |||
| ベリー系 | ブルーベリー | ||
| ブラックベリー | |||
| ラズベリー | |||
| イチゴ | |||
| クランベリー | |||
| イモ系 | 菊芋 | ||
| 里芋 | |||
| ジャガイモ | |||
| ナッツ系 | アーモンド | ||
| クルミ | |||
| 野菜系 | ネギ | ||
| 玉ねぎ | |||
| ガーリック(ニンニク) | |||
| エンドウ豆 | |||
| ツタンカーメン | |||
| ソラマメ | |||
| ミョーガ | |||
| アスパラガス | |||
| ジンジャー | |||
| 他 | イチジク | ||
| アケビ | |||
| モモ | |||
| ナシ | |||
| 洋ナシ | |||
| リンゴ | |||
| ポポー | |||
| フェイジョア | |||
| 梅 | |||
| ビワ | |||
| クリ | |||
| 柿(次郎) | |||
| 山椒 | |||
| シイタケ | |||
| トリュフ (ドングリの木) | |||
| マツタケ (赤松) | |||
| お茶(300本以上) | |||
| オリーブ | |||
| サフラン | |||
| クコ |
設備
プロパンガス(給湯器):夏はお風呂に入れます.(簡易露天風呂?)
水洗トイレ(ウォッシュレット):500Lタンク2基設置 一次発酵・二次発酵させ,液肥として活用.(植野の手作り,w/谷垣氏)
井戸:12m 川本ポンプ・川本フィルターにて給水システム構築
テラス 約20m2の床面積をもつ鉄骨とパイプで作成.溶接の練習に.天井はテントで.
脇の小川から水を引き込み,川本フィルターを通して500Lタンクに貯めおき,井戸とは別の給水システムを構築.主として散水とニワトリへの給水とする.
電柵;約8000Vの直流電流を流す電柵で農園を囲んでいる.主としてサル対策.京大の犬山で開発された電柵(モンキーショック)で,サルが昇って,一番上の電線に手をかける習性を利用したもので,ネットにはステンレスの鋼線が編み込まれており,体に電流が流れるという優れものです.その効果は抜群で,一度学習すると,その群れ全部が寄り付かなくなる.電力は,欧米の牧場で使われているもので,6J(数十キロをカバーする力がある)あるもので,多少の漏電(草や枝などが電線に接触すると起こる)ではびくともしない.
電撃殺虫機:最初のころ,栗を収穫してみると,中に虫が入っていたり,穴が開いたものが多くて困ってました.山岳地なので,結構いろんな虫が寄ってくるので,電撃殺虫機を電柱に設置しました(東芝ライテック製のもので,紫外線をだす蛍光灯を2本備え,その間のグリッドに高電圧(3000V)をかけてあります.虫が光につられて寄ってきて,グリッドにぶつかるとバリバリという音を出して焼かれる仕組みです).これが動作して以来,栗には虫がほとんどつかなくなりました.残念なことに,季節に飛び交っていたホタルが全滅しました.
現在は,東芝ライテック製を2基(40W),Flowtron社製のランプ型を2基を農園の害虫管理に設置してます. (40W)
(40W)
また,鶏舎にはハエが寄ってくるので,大型のFlowtronを1基設置してます.これは,死んだ虫を受け取る受け皿がついており,あつめた虫は高品質のタンパク質であり,ニワトリに与えると,喜んでというか取り合い状態で食してくれてます. (80W)
(80W)
狩猟
農園を始めたころ,ソバの種を蒔きました.パイプハウスの中と外.しばらくたって,新芽がでて,成長してきたときに,外の葉がすべて草刈りでかったようになってました.これはシカだなと思い,ネットで策をこしらえたのです.それから数年経ち,パイプハウスの中で里芋を栽培し,さて収穫というときに,農園の中が一面土がほじくり返されて,里芋は跡形もない状態でした.イノシシの大群が来て,パイプハウスにかけてある金網などは大きな穴が開いたりして,本当にイノシシの運動場のような状態でした.家内は悲しんだのやら,残念に思ったと思います.農園を囲むようにブリキのトタンをめぐらし,イノシシが入れないように工夫はしたのです.それ以後,工事現場でコンクリートの中でつかう鉄の格子が売っていたので,200個買い込み,農園を完全に囲み,いわゆる鉄格子の壁を作りました.格子は10cm角なので,さらにネットをはり,小動物も入れないようにしました.
いろんな動物の被害にあったので,心底腹を立てた訳です.そこでたどり着いた一つのリベンジは狩猟免許をとって,シカ・イノシシを捕まえる試みでした.鉄砲の場合,山の中に入って,動物を見つけて鉄砲を撃つ訳ですが,そうそう単独で山の中で動物に巡り合うことはありません.集団でする狩りならば鉄砲は有効なんですが,私には仲間がいません.ですので,罠猟の免許を取得することに.そのためには,猟友会が開催する講習会に参加しました.講義を受け,小型の箱罠の組み立てを習いました.都道府県が実施する狩猟免許の試験を受けることに.試験場では,身体検査と筆記試験,そして実技がありました.見たことがある人がいるなと思ったら,猟友会の方たちが試験管なんですね.私の場合,実技なども問題はありませんでした.でも,前の方は,会場で持ち時間一杯ガチャガチャと音を立てて箱罠の組み立てをしていました.どうやら講習会を受けなかったようで,多分,実技は不合格だったと思います.私は,無事に合格.
農園の周りにくくり罠をいくつか仕掛けると,いろんな大きさのシカがかかりました.最初は勇敢に立ち向かい,ナイフでとどめを刺して,さばいたのですが,現在は,電気やりで仕留めてます.箱罠も購入し,米ぬかを餌にしてます.このところ,箱罠を仕掛けるたびに二頭づつ入ってます.捕獲したシカはさばいて,肉は冷凍保存.好きな方におすそ分けしてます.ある方法で保存すると,生臭さは残りません.農園でとれた里芋などと一緒に煮込んで,カレーなどにしたら結構いけます.
イノシシはなかなか取れません.多分,絶対数が違い,圧倒的にシカが多いので,シカがさきに罠にかかってしまうのでしょう.山の上に罠を仕掛けるとよく獲れそうですが,重量のあるイノシシを下におろすほど体力はなく,農園の周りの平地に罠を仕掛けるだけです.
狩猟には猟期(冬場)があり,鉄砲には日没から日の出までは狩猟できませんが,罠猟にはそのような時間的規制はありません.ただ,猟期以外の時期では狩猟できないことになってます.ただし,夏場は,害獣駆除の目的で,市町村が認めれば(地域の猟友会がそれにあたる),狩猟ができ,しかも,一頭あたりいくばくかの補助金をもらえることになっています.私は大阪在住で,免許は大阪で取得し,三重県では狩猟許可をもらっているので,地元の猟友会には入れてもらえず(大阪の猟友会には所属してますが),害獣駆除の資格がありません.ところで,冬場の許可は都道府県の管轄ですが,夏場の許可は市町村なんです.お役所仕事ですね.猟友会もその管轄内で狩猟を許可されているものには,どこの猟友会に所属してようと,獣害駆除に関してはもっとオープンであるべきです.ちなみに,2021年度から冬場でも獣害駆除として補助金がもらえるようになったと聞き及んでいます.でも,私は対象外なんでしょうね.
よく罠やその部品などを購入する九州の業者さん(日本一安い罠の店)が連絡してきて,大阪の猟友会にたくさんのカタログを配布してます.こまごました部品は入手先が限られるので,カタログが手元にあればうれしいですね.